
ロサンゼルス国際空港|カリフォルニア(米国)
軌跡 3「情熱」
アジアから北米まで
2000年、タイから帰国し、しばらくすると、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど東南アジアの担当になった。コラソン・アキノ女史(フィリピン第11代大統領)が、本社・取締役に就任された翌年でもあり、私はフィリピンの看護師が日本で活躍する可能性を調査する特命プロジェクトに駆り出されることになった。電機メーカーであるものの、アキノ取締役は、フィリピンと日本との懸け橋にという強い使命感から、提言されたのだろう。私は、通常の貿易業務を離れ、プロジェクトに取り組むこととなった。会社が持つ人脈をたどって医療機関に意見を求めていったものの、「人の命を預かる仕事に、外国人看護師を受け入れるのは困難。」という意見で、閉鎖的な考え方も見え隠れした。外国人看護師の受け入れをするという経済連携協定が、フィリピンと日本との間で署名されたのは2006年なので、六年の歳月を要したことになる。
当時、私はアジア営業部の所属だったが、会社の大規模な組織変更があり、担当商品を絞る代わりに、広域を担当することになった。新たな海外事業本部での担当地域は、アジアと北米となった。アジアは長らく担当した地域でもあるので、軸足を北米へと移した。北米有数のリクライニング・チェア会社インタラクティブ・ヘルス(IH)との交渉では、私の所属する海外事業本部とIHとの間では、分厚い契約書を起案し、双方で契約書の修正案の応酬をしていた。そこには、「will」を「shall」にするといった修正をも含まれていた。そして、日本で交渉のテーブルについた際も、双方の意見がまとまらず難航していたが、そこに異を唱えたのが、IHのウォルマン会長である。ウォルマン会長は、日本企業との取引の経験が豊富にあり、契約書は重要事項を押さえておけば充分だと言われるのである。また、契約書の作成に要する時間と商機とのバランスを考えることが重要だとも言われていた。
ウォルマン会長を囲んでの会食で印象的だったことがある。それは、米国の消費市場では、靴を半年履いても気に入らなければ返品が出来るという話になった時だった。どの位の期間まで返品が受け入れられるかと聞くと、明確に定められているわけではないと言う。大方の反応は次の二つであった。一つは「米国の消費者は恵まれている。」という意見。もう一つは「米国は経営者に厳しい。」という意見。二つの意見と言っても、これはコインの表と裏と同じで、どちらの立場から見るかだけでの話で、本質は同じだ。するとそこに異論が出た。「米国の消費者は決して恵まれてなんかいない。」と言う。理由は、こうである。企業は利益を出さなければならない。しかし、高い確率で返品を受け入れるとなると、本来受け取るべき収益を圧迫するので、その返品を見込んで、今度は通常の商品の価格設定に織り込まれると言うのが理由だ。よって「返品をする消費者から生じる損失を、返品をしない消費者が負担しているのだ。」と。その時、私は論理的思考(Logical Thinking)の重要性を深く認識した。
ウォルマン会長が米国に帰国される際、私は担当者として、日本側の宿題と考えられる論点を整理し、その要旨を伝えた。そして、ウォルマン会長の言葉を待った。すると、「完璧だ。今、あなたが言った点をクリアすれば、すべてがうまくいくはずだ。」と言って下さった。当時、外国人(特に欧米人)のビジネスパーソンと話をする時は、できる限り論理的に話すよう心掛けてもきた。前述のように、国内営業部門から海外営業部門に異動した頃の私は、不安と焦りが尋常ではなかったが、その頃の私は、もうそこにはいなかった。後日、ロサンゼルスの事務所でウォルマン会長を交えて打ち合わせをしている時に、IHがホワイトハウスから商品の発注を受けたという話が舞い込んだ。ジョージ・W・ブッシュ氏(米国第43代大統領)がホワイトハウス入りを果たした翌年のことである。
情熱・主導権・プロ意識
会社の大規模な組織変更は、海外の現地法人にも及んだ。丁度その頃、私は海外戦略会議へ出席するよう指示を受けた。出席してみると、全取締役、全部門長が一堂に会するという会議で、私と同じ職位の人間は一人もいなかった。その議題の中で、シンガポールとマレーシアの現地法人を統合するという案が取締役主導で発議された。ある部門長は、シンガポールとマレーシアは、もともと同じ一つの国なのだから統合は良いと思うと同調し、大方がそのような意見だった。そこで、私は異議を唱えた。私は、電機製品の市場性の違いについて、商品ごとに具体的数字を挙げながら説明し、統合してもあまりメリットはないと主張した。頭の中では、両国の文化的背景の違いも考えながらのことであったが、そこまで話を掘り下げると、論点がずれてしまうので、表面上は、あくまでも電機製品の市場性の違いに論点を絞って主張した。発議した取締役は私の意見に反論したが、この取締役主導の事案に対し異議を唱えた人は、結局、私以外に誰一人としていなかった。しかし、このことが自分への自信に繋がっていく。
何故なら、結果として、シンガポールとマレーシアの現地法人の統合はなされなかったからだ。思い起こせば当時、仕事と並行しながら、担当国の事情を深く知るために、それと関連する本を読み漁っていたが、それが良かったのかもしれないとも思う。リー・クアンユー氏(シンガポール初代首相)や、マハティール・ビン・モハマド氏(マレーシア第四代首相)の著書などは、その国の国家観、世界観、歴史観なども読み取ることができて興味深かった。両国の関係について、リー氏は、「シンガポールは、1965年8月、この不幸な結婚生活から追い出されてしまった。」と表現し、マハティール氏は、「シンガポールの排除は分離独立と同じものではないが、人々は往々にして国全体の権益より自分たちの利益を優先する。」と表現した。民族構成比の違いが、考え方の違いに繋がっていることが見て取れる。
丁度その頃、経営方針発表会で、登壇した三洋電機貿易の社長が、社員一人ひとりに求めるものと題して話をされたことがあった。それは、「Passion、Initiative、Professionalism(情熱、主導権、プロ意識)の三つである。」と。それからというもの、「情熱、主導権、プロ意識」、これらを常に念頭に置きながら仕事に取り組むようになった。話は戻り、前述のように、社内には、英語のみならず、スペイン語、フランス語、ロシア語から、アラビア語、ペルシャ語、ビルマ語に至るまで、数多くの語学の専門家がいた。一方で、インドではヒンディー語が、フィリピンではフィリピン語が、それぞれ公用語であるものの、英語が広く使われているため、それらの国々の駐在員は、英語は必要とされても、ヒンディー語やフィリピン語までは必要とはされていなかった。しかしながら、中国(中国語)、韓国(韓国語)、タイ(タイ語)、インドネシア(インドネシア語)、ベトナム(ベトナム語)などの国々は、事情が大きく異なる。公用語が一つしかないため、言葉の問題が常に付きまとうのだ。それゆえ、大学でそれらの外国語を専攻していた人達は、その専攻した言語の国々に駐在することを強く願っていた。
当時、私は同僚にこんな話をしたことがある。「タイの駐在はとても充実していたけれど、一方で英語以外の外国語を習得することの難しさも痛感した。第一、単語を一から覚えていかねばならないのは、やはり大変だった。」と。また、その大変さを知っていたからこそ、次に駐在するのであれば、英語圏の国々か、言葉を学んだタイへの再駐在になることを願ってもいた。事実、タイの駐在を終え日本へ帰国した後も、タイ語のレッスンを続けていた。そして、「インドネシアやベトナムの駐在は、仕事は楽しくても言葉の習得が大変そうだね。」とも話した。しかし、会社の辞令というものは、得てして本人の意思とは関係なしに発令されるものである。そのような話をしていた私に、2003年の春、ジャカルタ(インドネシア共和国)への駐在が内示された。周りには、大学でインドネシア語を専攻し、インドネシアへの駐在を望む人もいたので複雑な心境にもなった。そして、このジャカルタ駐在が、自分の人生の潮目さえ変えてしまうことになろうとは、この時はまだ、知る由もなかった。
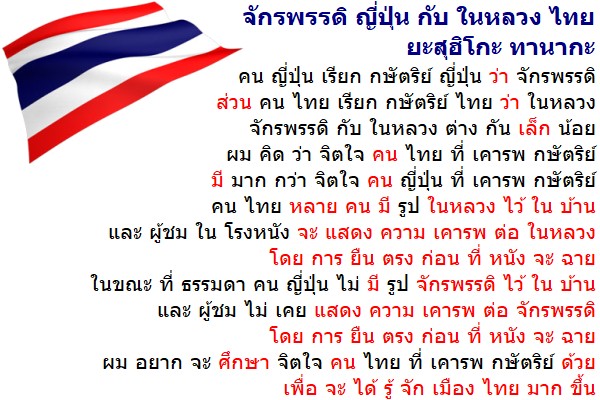
タイ語作文「天皇陛下とタイ国王」(赤い文字はタイ語講師による添削)|大阪

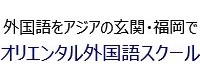
 英語
英語 ディレクター
ディレクター