
キング牧師・非暴力社会変革センター|アトランタ(米国)
軌跡 1「原点」
海外志向の原点
私、田中保彦の海外志向の原点、それは学生時代にある。雑誌「スコラ」での立花隆氏へのインタビュー記事、そして、落合信彦氏の自伝ノンフィクション「アメリカよ!あめりかよ!」に出会った頃にまでさかのぼる。立花氏は、大学時代に欧州を旅し、「自分の想像していたよりも、世界があらゆる意味で広くて深い。」と感じ、そして、落合氏は、「日本脱出を決心し、目をアメリカに向けた。自分の将来はアメリカにしかない。」と、米国の大学への入学を果たした。共に海外渡航に厳しい制限が掛けられていた時代の話である。私は自分の将来を考えた時、その頃から「海外を舞台に仕事がしたい。」と漠然とではあるが思うようになった。
人生初の海外旅行はその頃で、1987年、米国をバスで横断した。グレイハウンドバスの周遊券・アメリパスを利用して、ロサンゼルスからヒューストン、シカゴ、フィラデルフィアを経由し、ニューヨークまでの旅である。夜行便に乗り、翌朝には次の目的地に着くというスケジュールで、ホテル代をできる限り節約した。海外に行く機会なんて、そうそう無いという思いもあり、普段、日記を書かない私が、この時ばかりは今の気持ちを書き留めようと、米国で感じたことを毎日、日記に書き記した。そんな中、移動しているグレイハウンドバスの中で、私が携帯しているオーディオ・カセット・プレイヤーのスピーカーの音量を出来るだけ小さくして、音楽を掛けたことがあった。すると、私のそばに座っている黒人の女性が、「良い音楽ね。」と私を向いて微笑んだ。「すべてをあなたに|SAVING ALL MY LOVE FOR YOU」(ホイットニー・ヒューストン)である。その時、ホイットニー・ヒューストンは、ある人々にとって、誇りなのかもしれないと、その女性の表情を見ながら思った。
また、折角、米国に来たのだから、出来るだけ米国料理を食べたいと考え、中でもハンバーガーを食べる機会は多かった。ハンバーガーと言ってもバリエーションは豊富なので、余り飽きることもなかった。とは言え、その土地ならではの料理を食べることが出来るのは、旅行の楽しみの一つでもある。ニューオーリンズのクレオール料理は、米国でも特に美味しい料理と言われていて、ニューオーリンズが、かつてフランス領、スペイン領として栄えていたこととも関係しているらしい。クレオール料理店「ペール・アントニー・レストラン」で、ジャンバラヤを食べ、「さすが言われるだけのことはある。」と思った。と言うのも、ジャンバラヤは、スペイン料理のパエリアに起源があり、日頃、ハンバーガーなどパン食がメインだったがゆえ、米食の美味しさに、改めて気付かされたのだと思う。
米国で、興味深かった場所は数え切れないほど多くあるが、その内の一つが公民権運動の指導者であるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の遺志を引き継いで設立された非暴力社会変革センター(アトランタ)である。前年、コレッタ・スコット・キング女史(キング牧師夫人)が、私の通う西南学院大学の創立70周年記念講演会のゲスト・スピーカーとして初来日をされていたので、同センターには西南学院大学の講演会のポスター(日本語)が貼られていた。何よりも衝撃だったのは、そこで鑑賞したフィルムである。人種差別が激しかった時代を映し出したもので、トイレが「White(白人)」と「Colored(有色人種)」とで区別されていた映像、黒人が放水車で吹き飛ばされている映像、どれもが衝撃的だった。当時、歴代の米国大統領がすべて白人である中で、「もし、黒人から大統領が誕生するとすれば、それはキング牧師その人であろう。」と言われていたのも、なるほどと頷ける話である。米国横断は、私にとって、とても考えさせられる旅であった。
卒業旅行は先進国とは違う世界を見たいと思い、1989年、インドを鉄道で一周した。インド鉄道の周遊券・インドレイルパスを利用し、カルカッタ(現・コルカタ)から、マドラス(現・チェンナイ)、バンガロール(現・ベンガルール)、ボンベイ(現・ムンバイ)、デリーを経由し、カルカッタへと戻るのだ。ここでは、米国横断時に書いていた日記の続編として、同じ手帳にインドで感じたことを毎日、書き記していった。インド鉄道の車両は人であふれ、座席と天井の間の網棚には、乳幼児が寝ているなんてこともよくあり、まるで寝台車のようだった。そんな中、車両の二人掛けの対面式座席で、私の周りの三人が同じグループだったことがあった。昼食時間になると、その内の一人が、手元にある昼食を指して、「一緒に召し上がりませんか?」と聞いてきた。インドの民族衣装であるサリーを身にまとった女性で、私と年齢も近いようだった。私が遠慮すると、「食事は一緒にした方が美味しいですから。」と言ってきた。その気遣いに私は、インド人の優しさに触れたような気がした。
寝台車ゆえの出来事もあった。ベッドに寝ようとすると、対面はターバンを頭に巻いた男性だった。男性は寝る前、ターバンを外す様子だったので、どのようにしてターバンが巻かれているのか興味があったので見ていると、ターバンは頭の形に合わせた帽子に巻かれていた。ターバンは頭髪などを切らない戒律を持つスィク教徒が、長髪を束ねるために着用しているのだという。スィク教徒は、モーターサイクルに乗車する時でさえ、ターバンを外すことはなく、ヘルメットの着用が免除されていた。そう考えると、ターバンを外した姿を拝見できるのは、寝台車など限られた場所になる。インドを旅するまで、インド人といえば、ターバンを頭に巻いているというイメージがあったが、インド人の80%以上はヒンドゥー教徒なので、数%に過ぎないスィク教徒のターバンがそれだけ特徴的だったということだろう。
鉄道で旅してると、駅で、チャイ(ミルクティー)や、ラッシー(ヨーグルトドリンク)、サモサ(ペイストリー)、ドーサ(クレープ)などの売り子が、ひしめき合っているのは、よく見かける光景だ。ある時、駅のプラットフォームを移動していると、「Japanese」と書かれた張り紙に目が留まった。海外を旅していると、「Japanese」という言葉には自然と反応してしまうものなのだ。近付いてよく見ると、それは、「Japanese Red Army(日本赤軍)」のメンバーが国際指名手配されているというポスターだった。当時、日本赤軍の表立った活動を聞き知ることはなかったが、それはある種、時代の爪跡と言えるのかもしれない。
インドで、興味深かった場所の一つにタージマハル・ホテル(ボンベイ)がある。インドで最初の五つ星ホテルで、ホテル内のインド料理店「タンジョール」で注文したターリー(小さな器に盛られた料理のセット)は、それまで私が旅で出会ったインド料理とは違い、さほど辛くもなく上品な味わいだった。ロビーではインドの国鳥である孔雀の羽根で調度品のほこりを払っているホテルマンがいて、その孔雀の羽根に、私はインドの品格を見たような気がした。そして、時は過ぎ、昭和天皇の国葬である大喪の礼の日を私はインドで迎えた。現地の新聞の一面は、昭和天皇に関する記事で埋め尽くされていた。天皇崩御の際も、インドは喪に服したほどで、自国の国家元首に対してならいざ知らず、外国の元首に対して喪に服するというその敬虔さは、私に海外から見た日本というものを深く考えさせる機会となった。
チットールガルという町ではクリケットをしている少年たちと出会った。人口は二万人程だという小さな町で外国人は珍しいらしい。そこでは、少年たちと一緒に映画を観に行ったりして過ごした。映画館の席は、まだカースト制度の名残をとどめていて、インド人はそれぞれの分に応じた席に必ず収まるらしいが、外国人はどこでも選べるということなので、一緒に座ることにした。映画が終わると、私は今後の予定を告げて少年たちとは別れたが、夕方、駅の待合室にいると、少年たちの一人がやって来た。「夕食は取ったの?」と聞くから「まだだよ。」と答えると、「家で一緒に取ろう。家族の了承は取っているから。」と言ってきた。
結局、その少年の家で特製インド料理をご馳走してもらうことになった。お母様が食事を作って下さり、お父様と少年とで一緒に食事を取るという思い出深い夜で、少年からは自宅の住所を書いたメモを受け取ったので、日本に戻ってからも必ず御礼をしようと心に決めた。食事を終えると、少年はわざわざ駅まで見送ってくれ、夜行列車に乗り込む時、少年は言った。「外国人旅行者は物を盗まれやすいから、気を付けてね。」と。その時、特に気にも留めなかったが、少年の言葉の意味がやがて分かるようになる。翌日、デリー駅に着き、目的地を巡って駅に戻るとストライキだと言うので列車は動かない。その日も夜行列車で次の都市に向かう予定で、前の米国横断時も日程の都合上、バスステーションに泊まることはあったので、このデリー駅ではバックパックを枕代わりにし駅に泊まることにした。
翌朝、起きて見ると、パスポートと財布は身に着けて無事だったが、それ以外の全ての荷物は盗まれてしまっていた。復路の航空券、カメラ、撮り終わったネガフィルム、少年の住所を書いたメモ、日記、現地で買った珍しい香辛料の数々、そして着替えなど全てである。撮り終わったネガフィルムが一番の損害だった。旅を最初からやり直すわけにはいかないからである。航空券は再発行すれば済むし、カメラも買い直せば済む。大概のものはお金があれば元に戻すことができる。しかし少年と撮った写真はもう戻っては来ないのだ。それに加えて、少年の住所まで分からなくなってしまった。きっと少年はこう思うだろう。「あの日本人に住所を書いたメモを渡したけれど、それっきり・・・。」またネガフィルムに加え日記まで盗まれたので、記憶でしか想い出をたどれなくなってしまった。前述のように、日記は、米国横断時に書いていた日記の続編として、同じ手帳に書き記したので、米国での日記も同時に失ったことになる。現地の警察署では、事情聴取の上、被害届を提出した。インドで最も英語を話したのはこの警察署かもしれない。このインドがその後、違う形で私の人生に関係してくることになる。
国内営業部門へ
1989年、三洋電機に入社し、国内営業部門である三洋電機九州販売に配属され、社会人生活は始まった。勤務地は、生まれ育った福岡である。入社して半年が過ぎると、三洋電機のコマーシャルに、ホイットニー・ヒューストンが起用され、「Sanyo Heat Beat '90」と銘打ったキャンペーンでは、全国ツアーがなされた。私は、会場となる福岡国際センターで、本人が歌唱する姿を目の当たりにしながら、米国横断時に彼女の歌声を聴いていた日々を思い出し、ホイットニー・ヒューストンは、私にとって、誇りとなっていた。1990年、鹿児島営業所に転勤となり、セールスとして、サンヨー薔薇チェーンやダイエー、寿屋、ベスト電器、マツヤデンキ、山形屋などを担当した。この鹿児島営業所の同僚に、のちに妻となる女性がいた。1992年、熊本営業所に転勤となり、サンヨーサテライトシステムやダイエー、寿屋、フタバ、新出光などを担当した。結婚したのはこの頃である。1994年、北九州営業所に転勤となり、ミスターマックスやニチイ(現・イオン)、長崎屋、西友、寿屋、丸久、マツヤデンキ、ロヂャース、ウォッチマン、D&Dなどを担当した。国内営業部門で、七年の月日が過ぎていた。
国内営業で学んだことは多々あるが、一つ挙げるとすれば、ポジティブ思考(Positive Thinking)で行動することが大事だということだろう。売れない理由を考える暇があれば、どうすれば売れるかに知恵を絞ったほうが、より生産的だということになる。国内営業で経験を積みながらも、ゆくゆくは、「海外を舞台に仕事がしたい。」という思いは、変わらず持ち続けていた。そもそも、三洋電機の社名の由来は、太平洋、大西洋、インド洋に代表される世界市場に目を向けて事業を展開しようというところにある。当時、入社以来ずっと楽しみにしていたことがあった。それは、現況書の提出である。現況書には、希望職種や希望勤務地を書く欄が設けられていて、現況書を書くたびに、希望職種には海外営業部門、希望勤務地には北米と書いていた。そして遠くない将来、いずれ叶うだろうとも考えていた。
1996年の社内報で、本社・会長の「言葉は英語、通貨はドル、思想はコラボレーション」という記事を読み、改めて意を強くした。丁度その頃、任意の時に連続五日のリフレッシュ休暇が取得できるということで、前後の土日を加えて九日間の休暇を取らせてもらった。妻と一人娘を連れ、目的地は英国。大英博物館、ビッグ・ベン、タワーブリッジ、バッキンガム宮殿、トラファルガー広場と見所は多くあった。そして、ピカデリーサーカスで「SANYO」のネオンサインを見た時、「海外を舞台に仕事がしたい。」という思いは一気に駆け上がった。帰国後、「現況書の提出だけでは足りない。行動に移す時だ。」と考え、労働組合の九州支部長に電話を入れた。「海外を舞台に仕事がしたい。」と、希望を伝えると、労働組合経由で、海外事業の要である三洋電機貿易まで話を繋げて頂いた。その後、同社の取締役人事総務部長が福岡に来られる機会があり、九州支部長と共に面談が設けられた。その時、「社内公募で海外派遣要員を募集するので、希望するのであれば応募するように。」と告げられた。
実施要領によると、原則として現在、海外関連業務に従事していない人を対象とし、応募に関して人事部から職場に一切通知しないので、応募者も職場に通知せずに受験せよということだった。横槍が入ることを防ぐためである。応募及び選考は全て水面下で、事実、連絡先は自宅とし職場は不可であった。担当地域はアジア、舞台は整ったのだ。その頃には、「自分の将来はアジアにある。」という気持ちになっていた。応募用紙には国内営業の経験を根幹にし、インドを切り口の一つとして加えながら書き上げた。ただ、インドでのトラブルは仕事とは関係ないので、インドの市場性を中心に取り上げた。インドは現在とは違い、保護貿易主義が強い市場であった。そして応募書類を送付し、大阪の本社で面接があった。何日位待っただろうか。しばらくして自宅に連絡が入った。本社の人事部からで、三洋電機貿易への異動決定通知だった。私の人生を大きく変える転機、それは、この瞬間にあったのだと思う。

ピカデリーサーカス|ロンドン(英国)

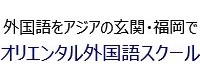
 英語
英語 ディレクター
ディレクター