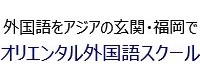SETRINDO|ジャカルタ(インドネシア)
軌跡 4「岐路」
ジャカルタへ駐在
新たな駐在先であるSETRINDO(SANYO Electric Trading Indonesiaの略)は、私を含めて日本人が三名となったが、二人は大学でインドネシア語を学んでいた。数ヵ月すると、その内の一人が転出をされ二名体制となる。駐在先は、三洋電機貿易と現地資本との合弁会社として設立されたものの、持株比率の変更により、新体制下では、社長と副社長はインドネシア人になった。もう一人の駐在員は、インドネシア人女性と結婚をされ、駐在も十年を超えていた。平たく言えば、上司はインドネシア人で、同僚はインドネシア人の奥様を持ち言葉の問題も何不自由なく生活をされているという環境だった。それゆえ、私にはインドネシア語の習得が課せられている。そこで、<Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya>の門を叩いた。現地の大学のインドネシア語コースである。世界最大のイスラム教徒数を抱えるインドネシアであっても、信仰の自由は憲法で保障されており、この大学はその名の通り、カトリックのミッション・スクールなのであった。
仏教国のタイでは仏暦が採用されていたように、国民の90%近くがイスラム教徒のインドネシアでは、イスラム暦に基づいて宗教行事が決められる。イスラム暦とは、イスラム教の預言者・ムハンマドの聖地・メッカからの移住を紀元とする暦で、一年が354日の太陰暦である。私が暮らし始めた西暦2003年は、イスラム暦1424年であった。その中でも、ラマダンは、イスラム暦の九月で、聖なる月とされており、この月においてイスラム教徒は日の出から日没にかけて、一切の飲食を断つなど、様々な欲望を抑えることにより、空腹や自己犠牲を経験し、自身の信仰心を清めると共に、恵まれない人々の気持を分かち合うという。ラマダンは、私にとって、信仰というものを深く考えさせられる月となった。
ジャカルタでは、ポンドック・インダー・タワーというサービスド・アパートメントで暮らすことになった。一階には、レストラン・パピロンがあり、レストランの外にはプールが隣接されていた。私は、屋外のプールサイドのテーブルで食事をするのが、何か南国らしい感じがして好きだった。パピロンは、比較的、名前が知られているレストランのようで、タクシーに乗車した際も、ポンドック・インダー・タワーでは通じなくても、レストラン・パピロンと言えば通じたなんてこともあった。また、アパートメントには、私の他にも日本人が暮らしていて、その方は警察官で、インターポール(国際刑事警察機構)・インドネシアに出向していた。私は一民間人だが、その時、日本からは、官民問わず海外へ飛び出しているのだと改めて思った。
ジャカルタには、ブロックMという日本人向けの飲食店が多い一画がある。そこで、私よりも先にジャカルタに赴任されていた日本企業の駐在員とお会いする機会があった。ジャカルタの前は、バンコクに駐在されていたとのことで、駐在経験に裏打ちされて繰り出される話題は、どれもが興味深いものばかりだった。その駐在員は、ジャカルタにあるアヤム・ゴレン(フライド・チキン)の名店「ニョニャ・スハルティ」にも連れて行って下さった。看板メニューでもあるアヤム・ゴレンは、もちろんとても美味しかった上、一緒に注文したソト・アヤム(チキン・スープ)は、絶品だった。それからしばらく、私は、どこの店に行っても、メニューにソト・アヤムを見つけると、必ず注文するようになった程である。
そして、ジャカルタの生活にも慣れてきた頃、私は、インドネシアの古都・ジョグジャカルタまで、旅に出ることにした。前述のように、世界最大のイスラム教徒数を抱えるインドネシアだが、イスラム教が渡来したのは13世紀らしく、ジョグジャカルタには、世界最大級の仏教寺院であるボロブドゥール寺院があり、その建設がなされた8世紀、この地はまだ仏教国だった。そこで、ジョグジャカルタまでは鉄道で移動することにし、インドネシア鉄道には、エグゼクティブ・クラスの車両があるので、それを体験してみることにした。エグゼクティブ・クラスの車両には、なんと警察官も同乗しており、また、まるで食堂車のように調理師もいて、そこでは、メニューが配られた。「coffee(コーヒー)」は、インドネシア語で「kopi」という。食べ物の欄に「bistik」とあったので、これは「biscuit(ビスケット)」のことだろうと、この二つを注文した。しかし、配膳されたのは、コーヒーとビーフステーキで、熱い鉄板の上に乗って出て来た。「bistik」というのは「beef steak」から派生した言葉なのだろう。おかげで、随分と贅沢なレッスンとなった。
インドネシアの隣国はシンガポールで、出張する機会は何かとあった。ある時、インドネシアへ帰国する際、ガルーダ・インドネシア航空(ナショナル・フラッグ・キャリア)で、シンガポール・チャンギ国際空港を離陸に向けて加速しているさなか、けたたましい音が機内に響き渡り、離陸は中止された。機体は、水平のバランスを大きく崩した状態のまま、滑走路上に停止した。乗客は客室乗務員の指示に従い、座席を立ち上がる人など誰もおらず、随分と長い時間、着席のまま待機となった。しばらくして、タラップで降りて機体を見ると、主脚が折れていた。それを見て、もし、離陸時には機体に異常が発生しなくても、着陸時に主脚が折れるようなことになれば、どうなっていたのだろうと思った。
2004年は、インドネシア史上初、直接選挙による大統領選挙が行われる年に当たり、デヴィ・スカルノ夫人(インドネシア初代大統領夫人|「デヴィ」とは、インドネシア語で「女神」の意味)が、ジャカルタにお見えになっていた。そして、「この大統領候補者は、21世紀のスカルノ」と流暢なインドネシア語で応援演説をされていて、翌日の新聞では、その記事が紙面を大きく飾った。その時、ある言葉を思い出した。「もしあなたが、相手の理解する言語で話したら、それは頭に届くだろう。もしあなたが、相手の国の言語で話したら、それは心に届くだろう。|If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.」ネルソン・マンデラ氏(南アフリカ第八代大統領)の言葉である。それは心に届く言葉というものを目の当たりにした瞬間となった。
時は過ぎ、やがて、大学のコースは修了したので、プライベートレッスンのインドネシア語スクールへと移った。最初のレベルチェックでは、「何でも良いので、インドネシア語で話をしてください。」と言われ、何とか言葉を選びながら話をした。すると、「駐在して一年とのことですが、大学はインドネシア語専攻ですか?」と聞かれ、「文法も発音も完璧なので、」と褒めて下さった。敢えて言えば、レベルチェックと言われたので、私が、普段、話しているインドネシア語ではなく、「文法と発音に細心の注意を払いながら話した」インドネシア語を、好意的に受け取って下さったのだろう。そしてこれを機に、普段から、文法と発音に細心の注意を払いながらインドネシア語を話そうと思った。
私は、ジャカルタ駐在も単身赴任でスタートしており、当初は、日本の夏休み頃に家族を帯同しようかと考えていた。一方、初駐在の地・バンコクでの家族帯同は単身赴任の一年後だったので、同じく一年間は現地の仕事を体得することに専念し、その後、家族を帯同するのも悪くはないとも考えた。結局、学年が変わる春休みが切りも良いだろうということで、春休みを目処に家族を帯同することにした。そして年が変わり、関係部署に家族帯同の申請をしたところ、海外事業本部の責任者から家族帯同のストップが掛かった。理由を聞くと本社からの通達で、海外駐在員の全社的な見直しをするとのことであり、一定期間、人事異動を凍結するのだと言う。その後も私は継続的に状況の確認は続けていったものの、好転しないまま、家族を帯同させているはずの春休みを迎えた。そんなある日、事務所にあるラジオから、聴き覚えのあるメロディーが流れてきたことがあった。「人間の証明のテーマ」(ジョー山中)である。異国の地で、ラジオから日本の曲が流れてくるなんて思いもしなかったし、♪Mama, do you remember(母さん、覚えてますか)♪の歌詞を聴きながら、日本が急に懐かしく思えた。
ある日を境に事態は急転する。妻が倒れ、集中治療室で治療を受けているとの連絡が入ったのだ。一時帰国し病院に向かうと、主治医から、ストレスによる免疫力低下が原因と考えられるとの説明を受けた。当時、長女が小学四年生、次女が幼稚園の年長と、母親一人で育てるのは大変だったろうと思った。また、父親の単身赴任先がジャカルタで、母親は入院という状況を考えれば、これから先、娘たちの不安はいかばかりだろうとも思った。人事総務部長に妻の状況を報告すると、やがて新たな人事異動が発令され、私の駐在は解かれた。現地法人での最終出社日には送別会が企画され、私が日本人だからか、社員の一人ひとりが「寄せ書き」を書いてくれていた。それを見て、駐在では、多くの人に支えてもらいながらここまで来たのだと改めて思った。一年目は、家族をジャカルタに帯同することを熱望していたが、ただこの時は、家族のいる日本へ帰国すること以外、考えることは何もなかった。
人生の岐路
帰国後の配属先は商品企画部で、担当商品は電子レンジ、担当地域は、アジア、オセアニア、中東、アフリカとなった。当時、我々が企画した電子レンジを、最も早くに導入したのがオーストラリアの現地法人であったため、私は担当者としてオーストラリアへ出張する機会を得た。訪問先はシドニーで、目的は電子レンジのプレゼンテーションである。その頃、プレゼンテーションの準備に時間があれば、心掛けていたことがある。それは自分で原稿を作り上げると、原稿の内容をICレコーダー(その昔はテープレコーダー)などに自分の声で吹き込むのである。そして、自分の声を聞きながら、発音の誤りを訂正すると同時に、発音の訂正が難しい場合は、同様の意味を持つ他の言葉に置き換えたり、文章そのものを組み換えたりして、完成度を高めていった。そして、まだ余裕があれば録音した音声を繰り返し聞き、プレゼンテーションの内容を頭に叩き込むようにもした。それは、電子レンジのプレゼンテーションの本番を翌日に控えた夜だった。ホテルの自室で一人、本番の予行練習をしながら、「海外営業部門に来て十年、仕事に向き合う姿勢は変わらないが、成長もしていない。」と、ふと思った。
その頃、十日間のリフレッシュ休暇を取れることになっていた。行く先は、家族との帯同が果たせなかったインドネシア。ジャカルタでは、私が駐在時に暮らしていたポンドック・インダー・タワーに宿泊した。そこのプールで、プールサイドチェアでくつろいでいる妻と娘たちの姿を見ながら、「家族帯同のストップが掛かる前、駐在の早い時期に家族を帯同しておけば、余計なストレスも掛からず、今頃、家族と一緒にここに暮らしていただろうに。」と思いを巡らせた。また、駐在先であったSETRINDOを訪問すると、私たち家族を会食に招待して下さった。おかげで、SETRINDOの仲間と私たち家族が一緒に歓談する機会にも恵まれた。副社長は避暑地として有名なスカブミに別荘を持っていらしたので、「週末そこへ泊まりませんか?」とも誘って下さった。私たちへの温かい配慮が何よりも嬉しかった。
私は、人生の岐路に立っていた。入社以来17年になるが、転勤(海外駐在を含む)は九回になっていた。転勤は色々な街に住めるので、どちらかと言えば好きなほうではあった。しかし、私が単身赴任した時に妻が倒れてしまうと娘たちはどうなるのか?そんなこと深く考えなくてもわかる。現在、私の目の前に広がっている光景、それがその答えだ。大阪は長らく住んだ街だが、身寄りがないことに変わりはないし、不安を抱えながらまた辞令を気にしながら生活を送るわけにはいかないとも思った。会社の仕事が充実していようと、社員の代わりはいても、夫、父親の代わりはいないという思いもあり、退職することにした。そして、家族に再び幸せな日々が訪れることを祈りながら、ここで再起動を図らなければならないと心に誓う。私がこれまでに培ったもので、今度は恩返しする番なのだ。

送別会での「寄せ書き」|ジャカルタ(インドネシア)